
こんにちは!るいままです。
息子が療育に通い始めて、あっという間に2ヶ月が経過しました。
また、1ヶ月目は3時間の短時間預かりでしたが、2ヶ月目からは10時から16時までの1日預かりがスタートしました!
長時間預けることに少し不安もありましたが、親の心配を吹き飛ばすほど息子が成長していて驚きと感動の日々を送っています。
この記事では、療育に通い始めて2ヶ月目で見られた息子の具体的な変化と成長について紹介していきたいと思います。
ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。
療育2ヶ月目でできるようになったこと
療育に通い始めて2ヶ月目、息子には目覚ましい成長がたくさんありました。
その中でも、変化が見られたのは大きく分けて以下の3項目です。
この項目の中で小さな成長がたくさんあったので、項目別に紹介していきたいと思います。
発語の増加
息子の発語については、意味を理解しているのかは不明ですが少しずつ話せる単語(略語?)が増えてきています。
完璧に言えるのは【青・泡・あっち】のみで、他は親にしか分からない略語ですが、今まで【電車(えやぁ)】しか言えなかったので、発語自体が増えたことに感動しています。
また、自分の意思を言葉で伝えようとする姿に日々成長を感じています。
特に感動したのは、絵本の「りんごちゃん、どこに行ったのかな?」という文章に「あっちぃ!」と返事をしてくれた時のこと。
感情が爆発して「そうだね!あっちだねぇぇぇ!!」と我ながら気持ち悪い反応をしてしまいました。
生活習慣の芽生え


療育に通い始めて一番驚いたのは、生活習慣が身についたことです。
親目線で特に変化があったと感じたのは、以下の4点です。
- ごみ・おむつを捨てられるようになった
- 「片付けてね」と声をかけると、所定の位置に戻せるようになった
- 靴を下駄箱にしまえるようになった
- 自分で靴を履く意志が芽生えた
どうしてできるようになったのか、ひとつずつ解説していきたいと思います。
ごみ・おむつをゴミ箱に捨てられるようになった
ごみについては、最初は「ごみポイするよー!」と声掛けをして一緒にごみ箱のところへ行き、私が捨てる様子を見てもらうようにしました。
何日か続けていると、自分からごみを拾って一人で捨てらるようになったのです。
ごみ以外のおもちゃなどを捨てたらどうしよう!と心配していましたが、ごみ以外のものは捨てる気配もなく、ごみ=捨てるものと認識しているようで関心しています。
そして驚いたのが、ここからです。
我が家では【ニオイポイ】というオムツ専用ゴミ箱をしています。
このニオイポイ、子どもに対しては少し面倒な仕組みをしていまして・・・
- ボタンを押して蓋を開ける(しかもボタンは2つあってややこしい)
- オムツを所定の位置から、グイッと押し込んで下に落とす
- 蓋を閉める(ちょっと力が必要)
という若干複雑な捨て方をする必要があるのです。
出来るかな?と思いながらも、ごみ箱と同じ要領で数回教えてみると・・・なんと、自分の力でできるようになったうえにオムツを替えると自分で捨ててくれるようになりました!
オムツのごみ捨てを成功させたコツ
1歳は何にでも興味を持つ年頃で、親が触っているものには何にでも興味を持ちますよね。
ニオイポイのごみ捨て3ステップは、普通にやっても覚えてくれないのでは?と感じた私は、その複雑さを逆手にとってゲーム感覚で取り組んでみました。
見てみて!このボタン!押してみて!開いたね!
→声をかけて興味を持たせる
これ押してみて!(おむつ落ちる)→おむつ消えたね!すごいね!
→”アクションを起こすと楽しい”と気づいてもらう
蓋閉めてみようか?閉められたら力持ちだね!できるかな?
→よいしょ!と声をかけて、できたら全力で褒める
複雑だと感じる工程も全てを息子の興味の対象にして、ゲームをクリアするような達成感を感じてもらうことで【楽しみながら取り組める】ように工夫してみたのです。
すると、息子はバイバイとオムツに手を振った後にきちんと捨てて蓋を閉めた後にパチパチと拍手をすることがルーティンになりました。
もちろん、捨てたあとは「捨ててくれてありがとう!」「上手にできたね!」と声掛けをしています。
「片付けてね」と声をかけると、所定の位置に戻せるようになった
今までは「お片付けしようね!」と言ったり、お片付けのうたを歌っても全く反応してくれませんでしたが、ある日突然おもちゃや絵本を片付けてくれるようになりました。
「ありがとう!」「綺麗になったね」と声をかけると嬉しそうにしている姿を見て、私も嬉しくなりました。
こちらは私から特別なアプローチはしていません。
療育施設で、周りのお友達がおもちゃの片付けをしている姿を見て【お片付け=所定の場所にしまうこと】だと理解してくれたのだと思います。
靴を下駄箱にしまえるようになった
キッズスペースで遊ぶ時に下駄箱に靴をしまう必要があった時のことです。
息子が靴を手に持ったと思ったら、自分の意志で下駄箱に靴をしまったのです!
さすがに上手く入れることは出来ないので片足ずつ違う段に入れていましたが、家で下駄箱にしまうことは全く教えていなかったので本当に驚きました。
その数日後、療育施設内に入る時に下記の指導をしてくださっていることを知りました。
この一連の活動を練習して周囲の大人が褒めることで、子どもの自信となり自己肯定感の向上に繋がるようにしているそうです。
息子の年齢だと全てを一人で行うことは出来ないので、先生が補助をしてくれています。
しかし、全てを補助するのではなく”靴下は半分だけ脱がせた状態からスタート”だったり、”自分から靴に足を入れるように促す”ようにしていて、息子が【自分でチャレンジする力】を育てくださっています。
「できたね!」と声掛けをすると、自分でパチパチしているという報告を受けて嬉しくなりました。
自分で靴を履こうとするようになった
先ほどと内容が同じになってしまいますが、自宅から出かける時に自ら靴を持って一生懸命靴に足を入れようとするようになりました。
そんな息子の姿を見て、親が率先して手を出すのではなく息子の取り組む姿を見守りつつ手助けをしていかなければいけないと感じました。
今まで全くできなかったこと、やろうとしなかったことに挑戦する姿勢を見せてくれるようになったのは療育施設での先生方の働きかけのおかげだと感じています。
コミュニケーション能力の向上


続いて成長を感じることができたのは、コミュニケーション能力についてです。
今までは【バイバイと言ったら手を振る】、【〇〇はどこ?と聞いたら指をさす】というように、私が言った言葉に対しての反応がメインでしたが、こちらにも変化が現れました。
- 自分の意志でバイバイできるようになった
- 聞き分けが良くなった
- ベビーサインや身振り手振りでする表現が増えた
- 歌や音楽に反応するようになった
自分の意思でバイバイできるようになった
今までは、私や周りから「バイバイ」と声を掛けられると手を振っていた息子が自分からバイバイするようになったのです。
すれ違うときや、エレベーターの中など自分のことを見てくれたり、声を掛けてくれる人に手を振るようになっていたのには驚きました。
それと同時に、人見知りだった息子がいろんな人に手を振っていることに感動すら覚えました。
療育施設でたくさんのお友達と遊び、帰り際にお友達とバイバイすることで身についたのかもしれません。
聞き分けが良くなった
外出前やお風呂に入る前など、持っていけないものを手に持っていた時に「また後で遊ぼうね」と声をかけると、その場に置いてバイバイと手を振ってこちらに来てくれるようになりました。
今までは【持っているものは絶対渡さないぞ!】という決意を感じていたので、聞き分けが良くなりすぎて正直かなり驚きました。
バイバイと手を振ることで、気持ちの整理が出来るようになったのだと感じています。
やはり、こちらについても先生方の声掛けやアプローチのお陰だと思いました。
ベビーサインや身振り手振りが増えた
今までは【いただきます・ごちそうさま】【美味しい】【痛いの痛いの飛んでけー!】くらいしか出来ませんでしたが、この1ヶ月間でベビーサインや身振り手振りの種類が増えました。
たったの5個?と思ってしまうかもしれませんが、5個増えただけでも発語がほぼない息子の気持ちが目に見えるようになることは感情を理解するための大きな一歩なのです。
熱い=食事や触れたものが【熱い】、暑い=外に出ていて【暑すぎる】と感じた時に両手の人差し指で肩を触ってくれます。(完全に我が家オリジナルサインです笑)


これが分かるだけでも【あ、熱かったのね】と分かるので親としても対処ができるので有難いです。
このサイン、食パンをトースターで焼いた後すぐに触った私が【熱いっ!!】と言って手をパタパタさせているのを見て一発で習得(?)したサインです。
発語が少ないので、こうやってコミュニケーションを取れるだけでも嬉しいんですよね。
定型のベビーサインではなくても、親子間で伝わるのであればオリジナルサインでも構わないので増やしていけたらいいなと思っています。
歌や音楽に反応するようになった
今までは、音楽や歌は好きでもリズムに乗ったり踊ったりすることはしなかった息子が少しずつ振り付けやリズムに乗るようになってきました。
出来るようになったのは【からだダンダン】【おおきなたいこ】【うさぎのダンス】の3曲です。
からだダンダンは、「びゅーんと風が吹いてきたよ」の手を大きく回すところ、おおきなたいこは「ドーン!ドーン!」の時にお腹を叩くところ、うさぎのダンスについては終始ピョンピョンするようになりました。
療育施設のレクリエーションで、ふれあい遊びや音楽に合わせてダンスをすることがあるので、音楽に合わせて反応する楽しさを先生やお友達に教えてもらったのかなと思っています。
療育に通い始めて2ヶ月が経ち、明らかに以前より息子とコミュニケーションが取れるようになったと感じています。
特に、この1ヶ月間は急激な成長を感じていて日々驚きの連続でした。
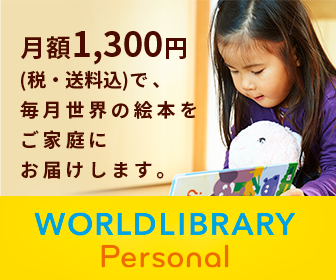
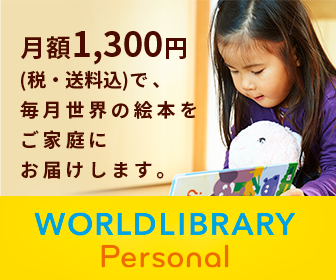
環境への適応と療育施設への安心感
1ヶ月目は施設内でもずっと泣いていた息子ですが、2ヶ月目に入るとお昼寝の時間もしっかり寝るようになり、環境にすっかり慣れたようで一安心しました。
療育施設の先生方も、息子の様子を詳しく伝えてくださるので安心して預けることができています。
療育でのアクシデントと先生の対応
2ヶ月目の療育中に、お友達に噛まれるというアクシデントが2回ありました。
連続して発生したため心配な気持ちはありましたが、送迎時に先生が状況と今後の対策をしっかり説明してくれたので、安心して任せることができると感じました。
このような丁寧な連携は、親として非常にありがたいです。
帰宅後に気になることがあれば、写真付きで施設とやり取りをすることも出来るので信頼度は非常に高いと感じています。
まとめと反省、今後の期待
療育に通い始めて2ヶ月目ですが、息子は本当に成長したと感じています。
特に生活習慣やコミュニケーション能力の向上は想像以上だったので、私だけではなく夫も息子の成長に驚いていました。
当初、夫は息子が療育に通うことに対して良い顔をしていませんでした。
そんな中、療育に通い始めた息子が急成長していることを目の当たりにした夫が【療育に通う決断をして良かった】とプラスに捉えてくれるようになったことも私自身にとっては嬉しい出来事でした。
親としての反省点
療育に通って成長している姿をみて、自分自身も日々の生活の中で息子への声掛けやアプローチの仕方を考えていかなければならないと痛感しました。
【もっと、こうしてほしい・こうなってほしい】と思うだけではなく、【どうしたら息子が楽しく取り組んだりチャレンジしたい!と思えるようになるのか】を最優先に考えて、声掛けや手助けなどのサポートをしていきたいと思います。
さいごに
療育に通いはじめて2ヶ月目、息子だけではなく親である私にとっても教わることが多いと感じた1ヶ月間でした。
今後も療育に通う息子の成長を報告していきたいと思いますので、また覗きにきていただけたら嬉しいです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
.png)
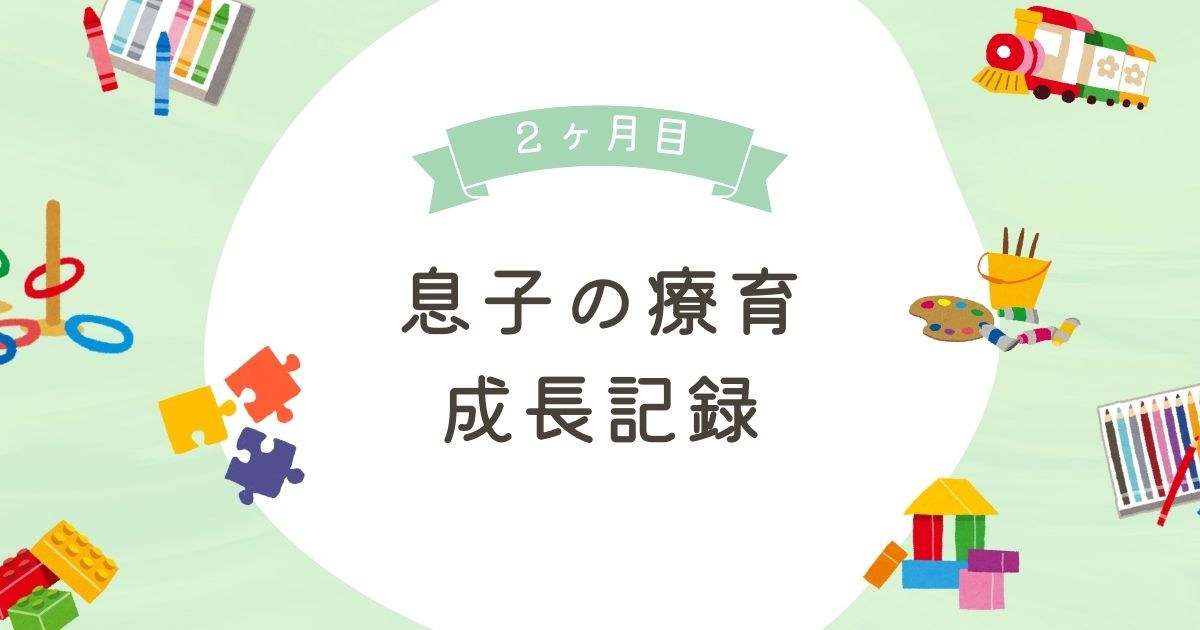
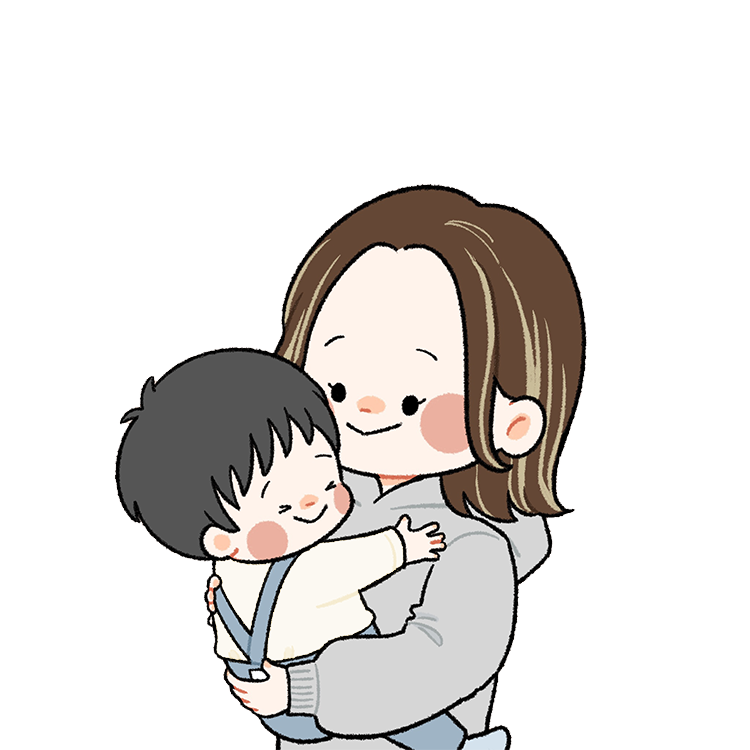


コメント